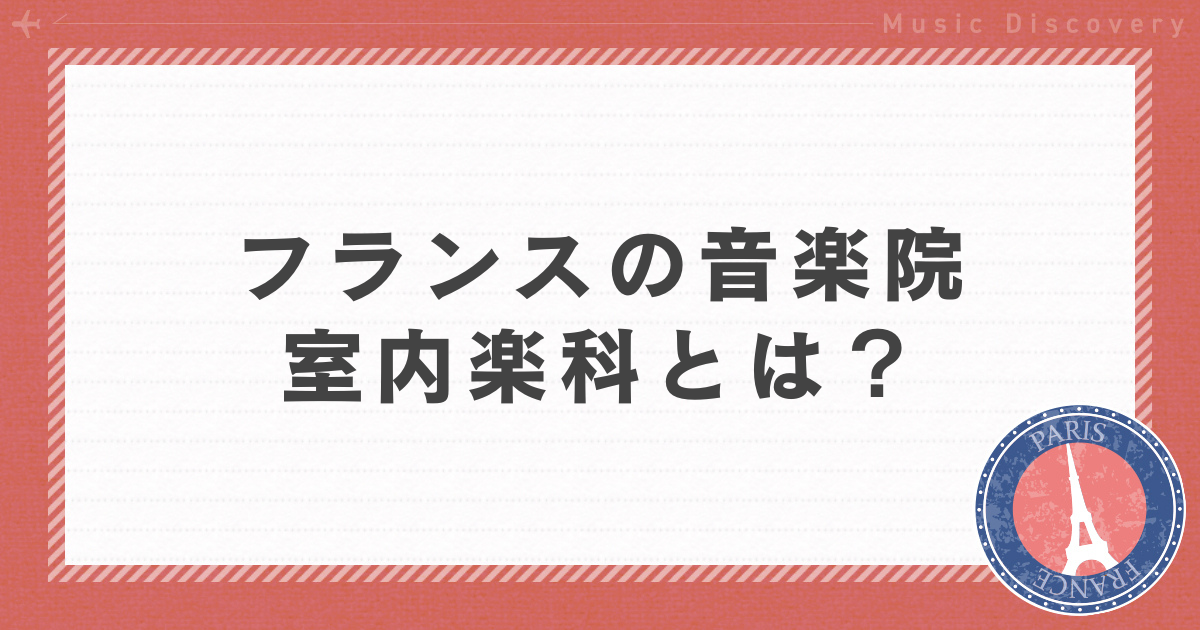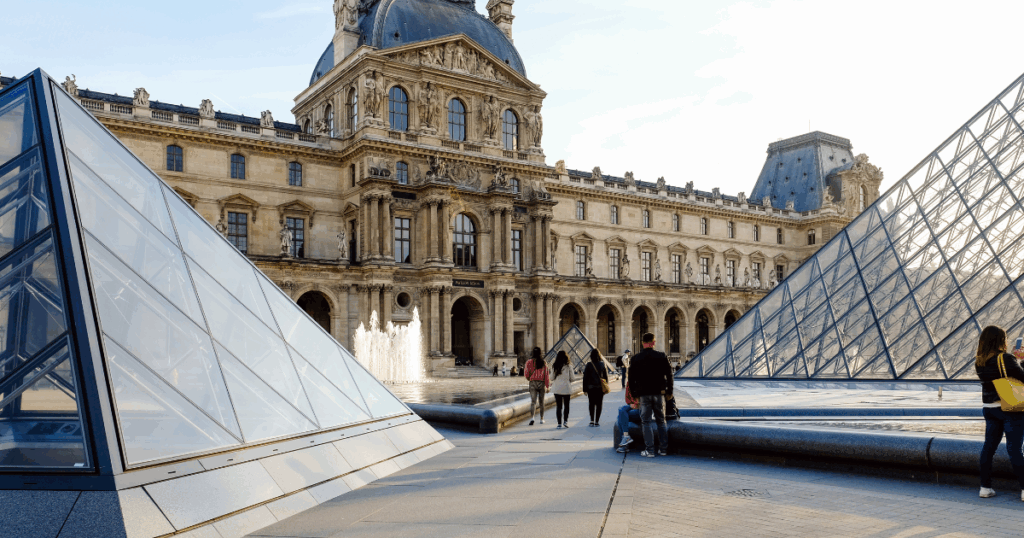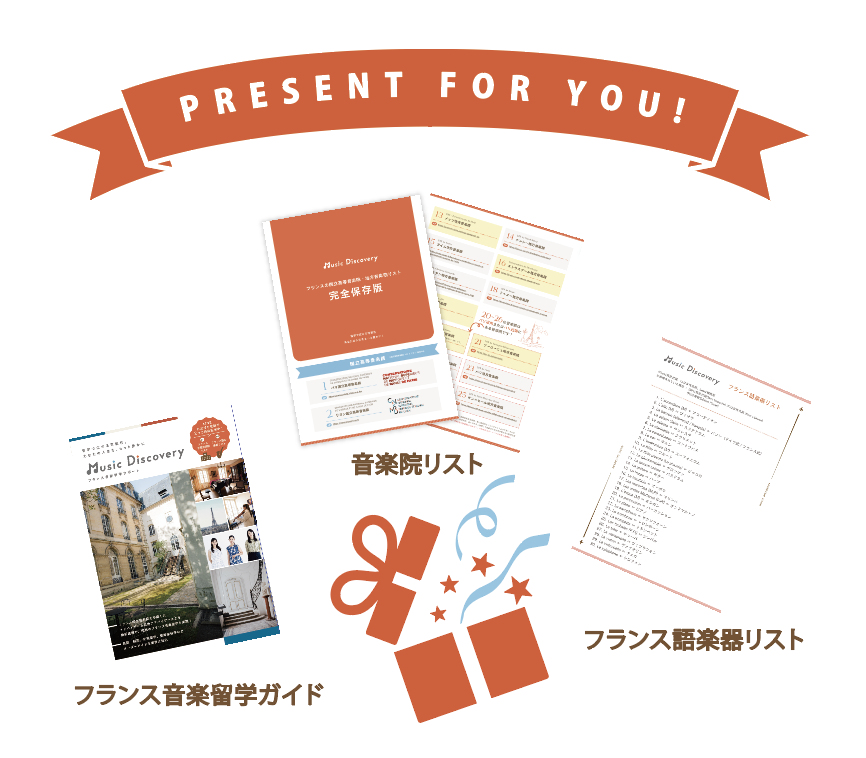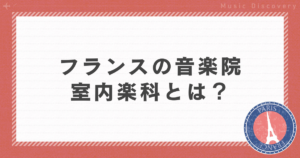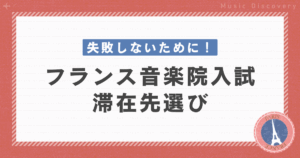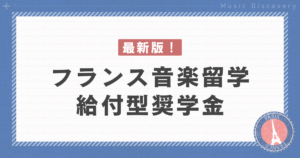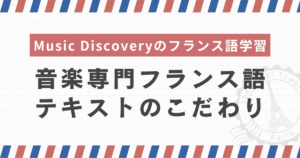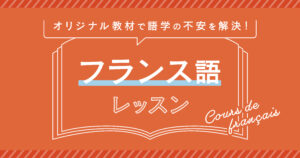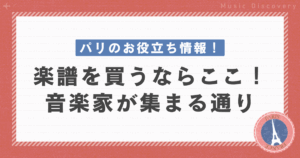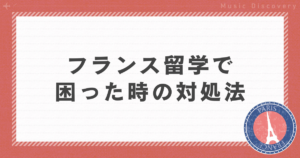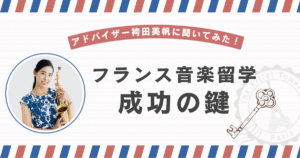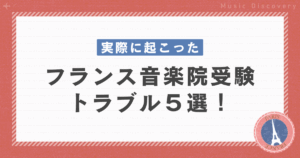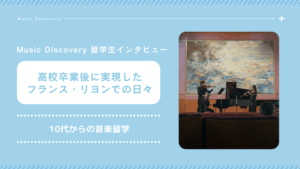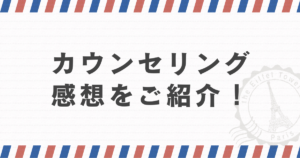フランスの音楽院でよく耳にする「室内楽科」。
日本の音大ではあまり馴染みがないこの学科ですが、実際にはどんな授業が行われ、どんな学生が受験しているのでしょうか?
本記事では、パリ地方音楽院、そしてパリとリヨンの国立高等音楽院の室内楽科を例に、具体的なカリキュラムや入試の特徴を経験者の視点からわかりやすく解説します。
「フランスの室内楽科って何を学べるの?」
「日本との違いは?」
と気になる方に向けて、留学準備や受験対策に役立つ最新情報をまとめました!
どんなグループがフランス音楽院の室内楽科に入れるの?
室内楽科の大きな特徴は、すでに結成されたグループ単位で入試が行われるという点です。
最も多い編成は弦楽四重奏。次いで、ピアノ三重奏(ピアノトリオ)やピアノデュオが一般的です。
そのほかにも、木管五重奏や管楽器アンサンブル、2台ピアノなど、比較的自由な編成で受験することができます。
中には、アコーディオンとギター、サクソフォーンとチェロといった、珍しい組み合わせで挑戦するグループもあります。
気の合う仲間とグループを組んで受験するのも良いですし、これまで経験のなかった編成に挑戦するのも新しい可能性を広げるきっかけになるでしょう。
室内楽科の修士号?フランスの室内楽科、本科と副科の違い

パリ地方音楽院、パリとリヨンの国立高等音楽院共に副科としての室内楽科と、本科としての室内楽科が、両方存在します。
ここで注意しなければいけないことは、国立高等音楽院の室内楽科本科だと修士課程にあたるので、メンバー全員が学士号を取得していなければなりません。
日本だとあまり馴染みがありませんが、修了したら「室内楽科の修士号」が取得できます。
「室内楽科だけに入るために留学する」 というのは珍しいですが、メンバーが決まっていて、全員が同じ志を持っていれば、もちろん挑戦できますよ!
フランスの音楽院で室内楽科を受験するためには
編成が決まったら、次は教授選びと受験プログラムの準備です!
どの音楽院にも、室内楽科担当の教授がいるので、その中から師事したい教授を選びます。
教授の専門楽器や、得意とする作曲家・時代と、グループで取り組みたいレパートリーと照らし合わせて、教授選びをしましょう。
受験プログラムは学校によって違いますが、20〜30分ほどの制限時間の中で、異なる時代の楽曲を組み合わせてプログラムを組むことが多いです。
音楽活動に繋がるカリキュラム!|室内楽科修士課程

パリ国立高等音楽院の室内楽科修士課程のカリキュラムでは、担当教授によるレッスンの他、座学の授業など、取らなければいけない単位や論文があります。
また、室内楽科ならではの特徴として、有名な室内楽グループによるマスタークラスの受講や、グループの活動に役立つ講義や、録音セッションなどもありますよ!
そして、室内楽科修士課程に在籍すると、学外で演奏する機会やアカデミーの案内なども回ってきます。
フランスの音楽院は、周辺の美術館や文化施設と提携している場合が多いので、頻繁に学生によるコンサートが行われているのです。
誰でも出演できるわけではありませんが、独自のプログラムに基づく企画が提携先の意向と合えば、出演団体として選んでいただけることもあります。
フランスの音楽院 室内楽科まとめ
フランスの音楽院における室内楽科の特徴や編成、受験方法についてご紹介しました。
自分の専門楽器以外の教授から指導を受けられる機会は、日本ではなかなか得られません。
しかし、フランスの室内楽科では多様なメンバーとのアンサンブルを通じて、新しい視点を学び、将来の音楽活動の幅を広げることができるのが大きな魅力です。
- 人と一緒に演奏するのが好きな方
- 既存のグループをさらにレベルアップさせたい方
- 将来、演奏活動や仕事に直結する経験を積みたい方
そんな方には、室内楽科への留学・受験は大きなチャンスとなります。
ぜひ本記事を参考に、フランスの音楽院室内楽科での学びを検討してみてください。